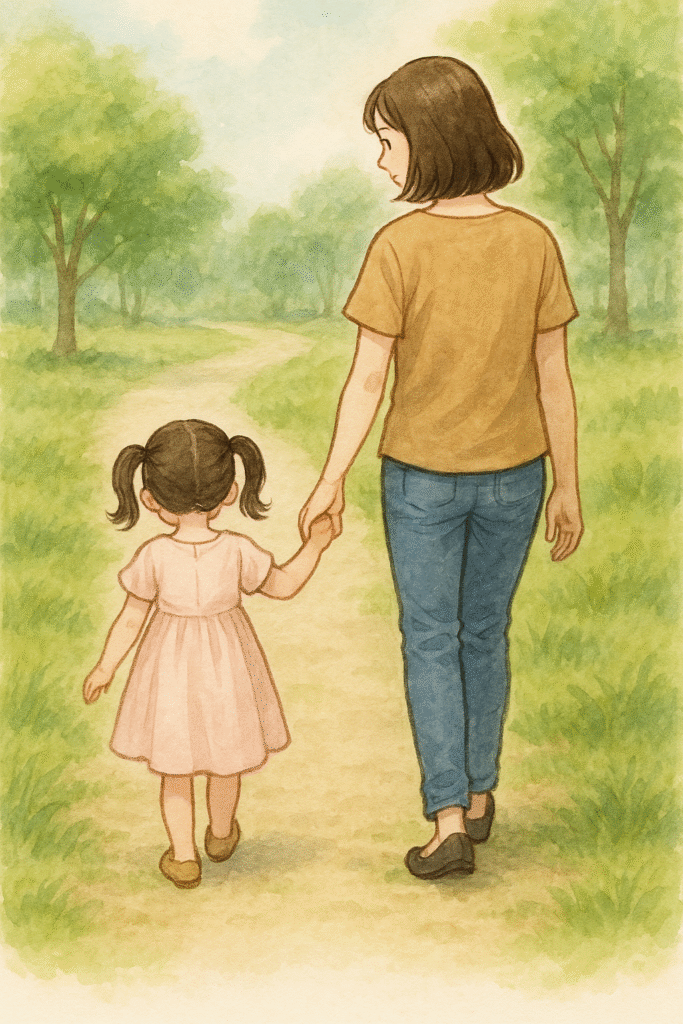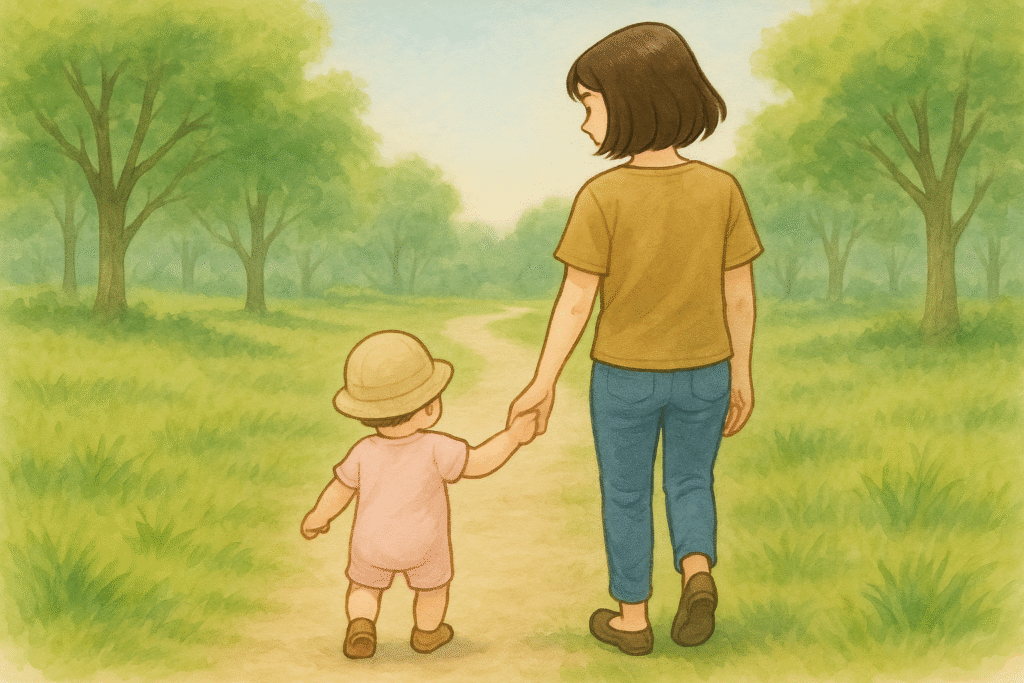
【支援への小さな一歩③】
迷い続けた先にたどり着いた、ひとつの“スタート地点”
ここから、新しい未来への一歩が始まりました。
前回記事はこちら📝 支援探しにたどり着くまで【支援への小さな一歩②】
🍼 1歳を迎えた頃の小さな気づき
ここちゃんが1歳を迎える頃、
他の子とちょっと違うかな? と感じる場面が、少しずつ増えてきました。
もともと機嫌の悪い時間が多く、
抱っこより おんぶ のほうが落ち着く子。
いわゆる「育てやすさ」とは、ちょっと違う育児の日々でした。
🕊 これまでにも感じていたこと
- 喃語があまり出ない
- 目が合わない
- 手を握り返さず、すぐパッと離す
- 触られるのを嫌がる
- はいはい・つかまり立ちが見られない
- おすわりのまま、くるくる回る
- おんぶしていないと泣き続けることが多い
- 眠りが浅く、夜中に何度も起きる
- 何をしても泣き止まず、泣いてはおんぶの繰り返し
- おんぶしていないと泣き続けることが多い
そんな毎日の中で、
1歳を迎える頃には、さらに気になる様子が見えてきました。
🌱 1歳頃に特に気になったこと
- 足の指がいつも曲がっていて力が抜けない
- 立たせようとするとつま先立ちになり、足裏が床につかない
- つかまり立ち・伝い歩きが見られない
- ときどき手がけいれんのように動く
けれど、一方で嬉しい変化もありました。
🌸 あやすと笑顔を見せてくれることが増えたり
🌸 表情が少しずつ豊かになったり…
不安の中にも、小さな安心の光 がちゃんとあったことを、今でもよく覚えています。
🏥 小児科での相談と専門機関へ
1歳前の定期健診のとき、
発達に詳しい小児科で相談をしました。
そこで言われたのは、
足の指の力の入り方について、専門機関で詳しく見てもらったほうがいいということ。
紹介された病院では、これまでの経過や様子を丁寧に見ていただき、
1歳を少し過ぎた頃に、診断がされました。
そして、すぐにリハビリを始めることをすすめられました。
先生の穏やかな口調が、今でも心に残っています。
🔍 一般的には、もっと後にわかることが多い
発達のスピードには大きな個人差があります。
「歩かない」「言葉が遅い」「落ち着きがない」…
そういう様子があっても、時間とともに自然に追いついていくお子さんも多いです。
だから、多くの場合は
🍼 1歳半健診や2歳児健診を経て、少しずつ特性が見えてくる
そんなケースが一般的だと思います。
私たちの場合は、特徴がいくつかはっきりしていたために、
例外的に早い段階で支援につながることができました。
💭 そのときの気持ち
診察で伝えられたとき、
正直「やっぱり、そうか」という気持ちがありました。
「子育てって、こんなに大変だったっけ?」
「なんでうちだけ、こんなに違うんだろう?」
そんな疑問が、全部つながったような気がしたのです。
もちろん、ショックもありました。
「これから、どうなっていくんだろう…」と、不安もありました。
でも一方で、
💡 「ようやくスタート地点に立てた」
そんな気持ちもあったのです。
迷いながら、情報を集めて、相談先を探して…
必死でやってきた日々が、少しだけ肩の力を抜かせてくれた瞬間でもありました。
🌱 早期に支援が始められたこと
1歳というタイミングで支援が始まったおかげで、
リハビリやことばの練習など、できることが一つずつ増えていきました。
専門家と一緒に「これからの育ち」を考えられることが、
私にとっては大きな安心でした。
まるで、
🛤 “行きたい場所の切符”をようやく手にできたような感覚 でした。
🌟 こうして早くから支援を受けられたことは、娘にとっても私にとっても、これから先へつながる大きな一歩だったと思います。
その子に合った支援を早めに始めることで、
🔸 発達を促したり
🔸 二次的なつまずきを防ぐことにもつながります。
実際に、今はさまざまな特性をもった人が
自分らしく社会で活躍しています。
✨ さいごに
「ふつうに育てる」よりも、
その子らしく育っていけるように、そっと寄り添うこと。
これが、私にとってずっと大切なテーマでした。
比べたくなることも、不安になることもありました。
でも振り返れば、当時気にしていた違いは案外ちいさなことだったなと感じます。
ここちゃんは、もうすぐ20歳になります。
迷いながらも一歩ずつ進んできたあの頃の私と、
そっと寄り添い、支えてくれた人たちがいたから——
今の私たちがあります。
👉 ここから始まったリハビリやことばの練習のことも、これから少しずつ書き残していけたらと思っています。